1. 退職を伝える4つの方法
退職の意思を伝える方法には、以下の4つがあります。
1-1. 対面で伝える(最も推奨される方法)
本来、退職の意思は直属の上司に対面で伝えるのが基本です。対面で伝えることで、誤解が生じにくく、退職日や引継ぎの話をスムーズに進められます。
対面で伝えるメリット:
- 直接話せるため、意図が正しく伝わる
- 退職後の関係を円満に保ちやすい
- 退職の意思が明確になり、引き止めが少なくなる
しかし、職場の環境や上司との関係によっては対面で伝えるのが難しい場合もあります。その場合は、次の方法を検討しましょう。
1-2. 電話で伝える(次に推奨される方法)
対面で伝えることが難しい場合、電話で退職の意思を伝えるのが一般的な代替手段です。
電話で伝えるメリット:
- 直接声で伝えられるため、誤解を防ぎやすい
- メールやLINEよりも誠意が伝わる
- すぐに対応できるため、退職の話を早めに進められる
ただし、電話ではお互いの都合が合わない場合があるため、可能なら事前にアポイントを取るのが望ましいです(詳細は後述)。
1-3. メールで伝える(最終手段)
メールやLINEで退職を伝える方法もありますが、これは基本的に避けた方がよいでしょう。
メールで伝えるデメリット:
- 退職の意思が軽く見られ、誠意が伝わらない
- メールの文面が誤解される可能性がある
- 返信が遅れたり、無視されるリスクがある
ただし、上司が多忙で電話に出られない場合や、どうしても電話が難しい場合には、まずメールで「退職についてお話ししたいので、お時間をいただけますか?」とアポイントを取る形で連絡するのは有効です。
1-4. 退職代行サービスを利用する(特定のケースで有効)
ブラック企業やハラスメントがひどい職場では、退職を伝えるのが非常に難しい場合もあります。その場合、退職代行サービスを利用するのも一つの方法です。
退職代行のメリット:
- 直接やり取りせずに退職できる
- 法的なトラブルを回避できる
- 会社側からの圧力を受けにくい
ただし、業者によっては信頼性が低いところもあるため、口コミや実績を確認して慎重に選ぶことが重要です。
2. 退職を電話で伝える際のアポイントは必要か?
電話で退職を伝える際、事前にアポイント(連絡の予約)を取るべきか迷う人も多いでしょう。
2-1. 可能ならアポイントを取るのが理想
事前に「退職についてお話ししたいので、お時間をいただけますか?」と連絡を入れることで、上司の都合が良いタイミングで話ができます。
アポイントの取り方の例:
「お忙しいところ恐れ入ります。お話ししたいことがありますので、本日または明日のどこかでお時間をいただけますか?」
このようにメールやLINEで事前に連絡しておけば、突然の電話よりもスムーズに話が進みやすくなります。
スポンサーリンク
2-2. アポイントが取れない場合は、適切なタイミングを見計らう
上司の連絡先がわからなかったり、事前に連絡を入れるのが難しい場合は、なるべく忙しくない時間帯を狙って電話をかけましょう。
電話をかけるのに適した時間帯:
- 午前10時〜11時(朝の業務が落ち着いた頃)
- 午後14時〜16時(昼休み明けで比較的余裕がある時間)
逆に、朝一番や終業間際、昼休み中は避けたほうがよいでしょう。
3. 電話で退職を伝える流れと例文
実際に電話で退職を伝える際は、以下の流れで話すとスムーズです。
3-1. 退職を伝える基本の流れ
-
挨拶と時間の確認
「お忙しいところ恐れ入ります。今、お時間よろしいでしょうか?」
-
退職の意思を伝える
「突然のご連絡で申し訳ありません。私、〇〇(名前)は、この度、一身上の都合により退職させていただきたいと考えております。」
-
退職理由を簡潔に伝える(詳細は不要)
「以前から考えていたことなのですが、〇〇の理由で退職を決意しました。」
-
退職希望日を伝える
「退職日は〇月〇日を予定しています。」
-
引継ぎや今後の対応について話す
「引継ぎなどについても誠意をもって対応させていただきます。」
-
お礼を伝える
「これまで大変お世話になりました。最後までしっかりと業務を遂行したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。」
4. 退職を電話で伝える際の注意点
4-1. 感情的にならず、冷静に伝える
どんな理由で退職するにしても、感情的にならず、冷静に話すことが大切です。特にブラック企業の場合、引き止めや圧力がある可能性もありますが、毅然とした態度で対応しましょう。
4-2. 退職の意思は明確に伝える
「辞めるか迷っている」と捉えられる言い方をすると、引き止められる可能性が高くなります。「退職を決意しました」と断言しましょう。
4-3. 必要なら退職代行の利用も検討する
どうしても退職を伝えるのが怖い場合や、上司の圧力が強い場合は、退職代行を利用するのも一つの手です。
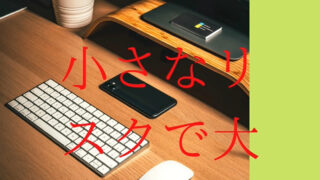

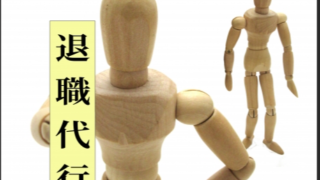


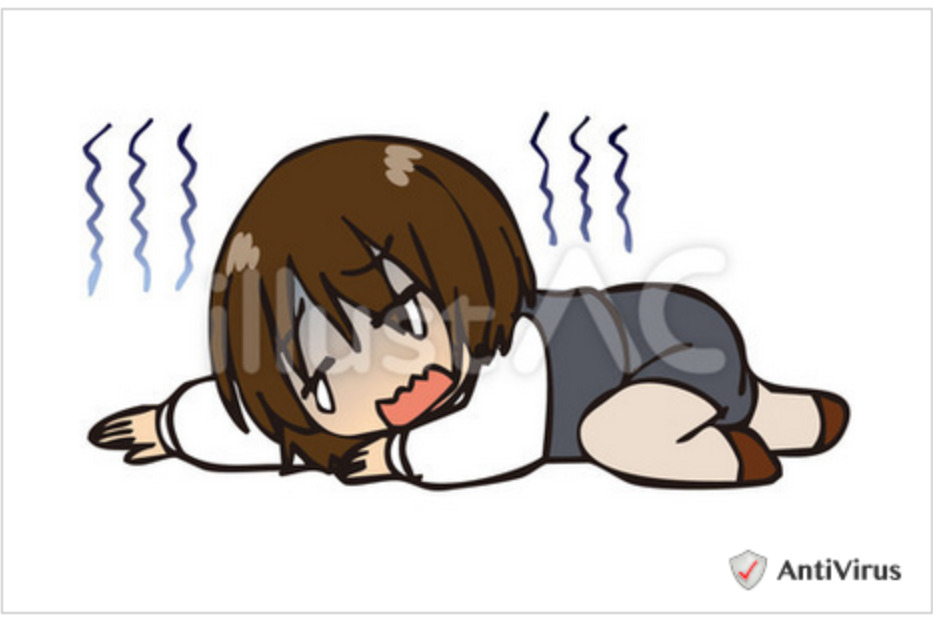


コメント